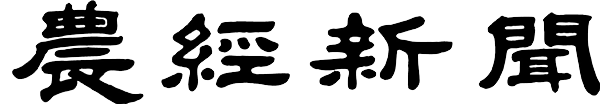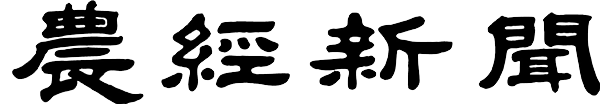
青果流通に特化した週刊専門紙
最新号(1月19日付)より
- 神明Gの青果卸 AI自動分荷導入へ 精度9割 属人化を解消 NTTグループと開発
- 青果物卸売市場の分荷業務については、電話、FAX、手書きなどアナログな方法による作業が多いだけでなく、担当者個人が持つ「暗黙知」が共有されないまま属人的な対応になっている。このため現場観点では長時間労働や作業ミス、経営観点では次世代の担い手確保や、生産性・品質の向上が課題。それを改善するためNTT AI-CIX(社家一平社長、本社=東京都港区)は、分荷をAIにより自動化する「分荷自動化サービス」を提供する。共同で開発に取組んできたのは神明ホールディングス(藤尾益雄社長、本社=神戸市中央区)。同社グループの青果卸における実証実験では、ほとんどの品目においてAIが自動生成した分荷案が、営業担当者による分荷結果と比較して9割を超える精度を実現。これを受けて今年中にグループの青果卸に導入する。
- 大型農家の台頭顕著 5億円超 20年で2.5倍に 農林業センサス
- 農水省が5年ごとに、わが国の農林業の生産構造、就業構造の解明や農山村の実態把握のために行っている「農林業センサス」。最新の2025年調査(2月1日時点)では、国内農家が減少するなか、大型農家(農業経営体)の台頭が顕著だ。とくに年間販売額5億円以上の大型経営体が1565に増加し、20年前(05年調査、630)の2.5倍にあたる。一方で200万から82万へと118万以上、6割近く減少した経営体の大半は、年間販売額1千万円以下。なかでも300万円以下が87.3%を占める。この傾向は今後ますます顕著になるものと思われ、販売力を持ち出荷先を選べる大型農家をいかに取込むかが重要になるものとみられる。
- サカタフェア2026 野菜90品種を一堂に 注目のBS新商品も紹介
- サカタのタネ(加々美勉社長、横浜市都筑区)は、展示会「サカタフェア2026」を横浜市内で開催した。同社開発の野菜品種90品種(小売用含む)をはじめ、農業用資材などを一堂に集め、生産者や種苗販売店関係者など500人が来場した。さらに、環境ストレス耐性を高める資材として注目されている「バイオスティミュラント」(BS)では、世界的な農薬大手・UPLリミテッド(本社=インド)のグループ会社であるアリスタ ライフサイエンス(東京都中央区)との共同開発による新商品「ロダルゴ」を発表した。
- スマート農業 効率的な農業推進で先進事例を視察 袋井市
- 静岡県袋井市はこのほど、先端的なスマート農業の取組みを視察するツアーを開催した。全国的に生産者の高齢化や担い手不足が深刻化する中、データやITなどを取入れた効率的な農業生産を行う経営体を増やしていくことを目的とする。この日は、生産者や学生など20人以上が参加し、完全人工光型植物工場でのレタス栽培、各種IT技術を活用した施設栽培の現場などを視察し、学びを深めた。
- レシピサイト運営各社 26年の食トレンド発表 「ブロッコリー」「冷凍野菜」など注目
- レシピサイトなどの運営会社が2026年の食トレンドを発表した。野菜では、指定野菜になる「ブロッコリー」や、夏野菜として認知が広まってきた「空心菜」などが注目され、「冷凍野菜」は今後さらに普及するとみられる。各社の予測を紹介する。
↑